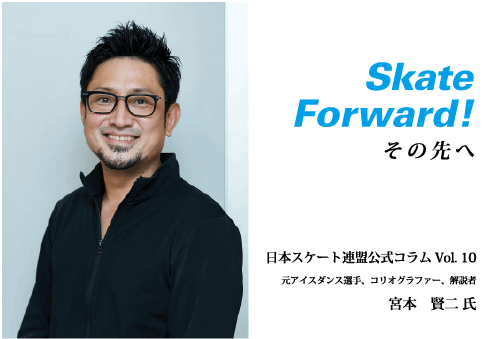Skate Forward! その先へ
Vol. 9
日本スケート連盟特任相談役
鈴木 惠一
3分25秒6から始まったスケート人生
世界選手権に7回出場うち5回優勝、500mで3度の世界新記録更新――スピードスケート黎明期の日本が生んだ破格のアスリート、鈴木惠一氏。とりわけ、1964年にオスロの競技会で、低地リンク500mの壁とされていた40秒を世界で初めて突破して以来、「世界のスズキ」と呼ばれるように。いまなお来日した海外の役員・関係者から「あのミスター・スズキか」と敬意を表される伝説的存在だ。だが、それだけの輝かしい経歴をもちながらも、1964年インスブルック、1968年グルノーブル、1972年札幌と、3大会連続出場したオリンピックでは一度もメダルを手にすることはなかった。勝利へのこだわり、金メダルへの熱い思いを持ち続ける、日本スピードスケート界の偉大なる先駆者に聞いた。
―― 13歳でスピードスケートを始めてから、60年以上この競技に関わっていらっしゃいますが、鈴木さんにとって、スピードスケートの競技の魅力は?
「魅力なんてありません。なぜかというと、環境が僕をスケートに導いたから。僕が生まれ育った苫小牧というところは、フィギュアはないけど、アイスホッケーとスピードスケートの街だから、そこに氷があれば、滑りたくて滑りたくてしょうがないわけ。田んぼのところに氷が張っていれば乗りたくなる。いまはいろんな遊びがあるけど、僕の時代は遊ぶものといったらスケートしかなかったから。もし他の場所に生まれていたらスケートはしていなかったと思います」
―― 苫小牧工業高校を卒業後、まずは地元の王子製紙に入社し、スピードスケート選手のエリート・コースに進まれたわけですが、1年後、王子製紙を辞めて明治大学へ。
「強くなるために海外留学に行きたかったけれど、行かせてもらえなかったので、会社を辞めて明治大学に入ったんです。ほかの大学からも声がかかったけれど、結局明治に入りました。明治大学からは一銭も出ないし、入学試験はあるし、条件は最悪だった。スケートをやるのはお金がかかるから、お金はほしかった。でも、それまでは恵まれた環境にいて、逆に歯車が狂った。あえて条件が一番厳しい明治を選んだことで、僕はたぶん強くなれたんだと思う」
―― 入学したものの、大学のスケート部の指導に飽き足らず、独学でウエイトトレーニングに励んだり、画期的なトレーニング法を編み出したりされたのはスピードスケート界では有名な話です。国内では、大学2年生から引退するまで、9年間で1回しか負けなかったそうですね。
「1968年に世界選手権で初めて勝ってからは、全部が違ってきました。世界チャンピオンのタイトルがついてまわるわけだから、国内では絶対に負けられない。世界で戦う人間が日本に帰ってきたら負けるわけにいかないんですよ。いつも勝ち負けに追いかけ回されて、今日は負けるんじゃないか、明日は1位になれないんじゃないかという恐怖心ばかり味わっていました。いつも、これでもか、これでもかというくらい練習して、試合後は『あー、今日も勝った。よかった』という気持ちしか残っていない」
―― それを続けていく原動力は何だったのですか。
「信念かな。『お前は、もう負けられないんだ』って、心に言い聞かせました。負けるわけにいかない。だから勝って、勝って、勝ちまくったわけだけど、それが逆効果だったんだよね。国内では誰もついて来られなかったから、トップから落ちる恐怖心からいつまでも逃れられなかった」

「初めて出た国際試合がインスブルック・オリンピックで、海外の選手全員が初めて見る選手でした。それまでも独学でソ連の科学者が書いたスピードスケートの専門書を読んだりして研究していたけど、オリンピックの期間中、実際にいろんな選手の後ろについて、技術はこうやるんだな、ああだな、こうだなというのを、納得いくまで習わせてもらいました。僕の座右の銘は『一歩後退、二歩前進』。僕は天才じゃないから、一生懸命一歩下がって、これだなと思う選手の後をついて習うしかない。初めてのオリンピックでは試合よりもほかの選手から学ぶことに一生懸命だった」
―― 鈴木さんは天才ではなかった?
「生まれながらの天才というのはいないんじゃないかと思う。天才っていうのは、たとえば野球だったら王貞治さんとイチローさん。2人とも記録を残したすごい人だと思います。3人挙げろと言われたら、3冠王を3回獲った落合博満さんも。天才かどうかは、長く続けて辞めた後、振り返ってみたときに初めてわかるものだと思う」
―― スケート人生のなかでもっとも思い出に残る試合は?
「もっとも忘れられないレースは、1968年グルノーブル・オリンピックで金メダルをもってこられなかったこと。人生でいちばん悔しかったことも、グルノーブルで負けたこと。世界中の指導者たちが500mの金メダルは鈴木だろうと言っていたのに、負けたんです。悔しくてたまらなかった。そうしたら、所属していた国土計画の堤義明社長が、金メダリストのエアハルト・ケラー(旧西ドイツ)を日本に呼んで、全日本選手権のなかでマッチレースをやらせてくれた。3本滑って、2本僕が勝って、1本は同タイム。これも人生で忘れられないレースになりました。でも、勝ったことはうれしかったけど、軽井沢の土俵とグルノーブルの土俵は違う。グルノーブルで勝っていたら、僕の人生は変わっていただろうね」
―― ケラーは鈴木さんのよきライバルだった?
「僕はライバルとは思ってない。ライバルは自分です。競技っていうのはね、1回勝てばもう負けられないんですよ。昔の人ってそうなんです。だから、大げさでもなんでもないんだけど、1位獲んなきゃ、2位も3位も一緒なんだっていう考え方をつねに持っている。そんな時代だったんですよ」
―― トップであり続けることは、並大抵のことではないですよね。
「でも、勝ってもすごい賞金をもらえるわけじゃない。だから偉い人にこう言ったことがある。賞状やトロフィーはいらないから、賞金をくれって。トレーニングや海外遠征にはお金が必要なんですから、現実的でしょ。僕は普通の選手だったら絶対言わないことを言うから、異端児扱いでした。「結果を出す選手がほしかったら、国際結婚をして、そこから生まれる子どもを選手にしたらいい」なんて言って、絶句されたりしていましたからね。でも、実際にスピードスケートにおいて、体格の問題は大きいと思う。僕は昔、生意気だとよく言われたけど、それだけの結果は出していた。もちろん生意気なことが、全部成功していたとは言わないけど」
―― 選手時代に、スケートをやっていたために、あきらめたことはありますか?
「ないです。9年間全部スケートに没頭していましたから。つらいか、つらくないかって聞かれたら、つらかったかな、どうかな?というぐらい」

「自分がやってきたことを教えていただけなんだけど、それが難しいのか厳しいのか、最初の3年くらいは選手たちが全然ついてこられなかった。僕が言っていることに対して疑心暗鬼になっているんだろうと思って、あるとき選手たちと一緒に自分もレースで滑ってみせた。そうしたら、短距離なのに僕に勝てたのが1人だけだったんです。ほかは惨敗。それからは厳しくても自分の言うことを選手たちが聞くようになったし、僕自身も根気強くやっていくしか手がないとわかったんです。指導者としては、インカレ(日本学生氷上競技選手権大会)で、第76回大会のとき、スピード部門が500、1000、1500、5000、10000、パシュートと6種目全部勝って完全優勝したことがいちばん指導者冥利に尽きた瞬間でした」
―― 現在のスケート界をどうご覧になっていますか。
「選手の肉体は超一流。ただ、理論的にはまだそうじゃない選手もいる。大人として理論的に話せることは大事で、フィギュアスケートだと、羽生結弦は自信をもって発言している。スピードの選手のなかでは、髙木美帆は自分自身をきちんとわかっていると思う。彼女はすごいね。前に「センゴ(1500)が強くなれば全部強くなれるな」って本人に言ったことがあったんですけど、本当に強くなった」
―― 最後に、鈴木さんの宝物とは何でしょうか。
「いちばんの宝物って言ったら、金メダルだろうな。ただし、自分は獲ってない。獲ったもののなかで……? それはない」
―― 世界選手権の金メダルは?
「世界選手権のメダルもそりゃすごいですよ。だけど、その上にオリンピックの金メダルっていうのがある。上があるなら獲りたいという気持ちがアスリートになくなったら、辞めたらいいと思う」
―― もし、いままでのキャリアを全部なくして、まったく違う何かになっていいと言われたら、何になりたいですか。
「僕は金メダルが獲れる種目のアスリートがいい。やっぱり金メダルのイメージがすごく残っちゃっているから。金メダル獲れる種目なら、どんな種目でもいいけど、首から金メダルさげてみたい。それができるなら、僕の一番の宝物になるけれど、獲れなかったからしょうがない」
―― では、スケートをやっていてよかったことは何ですか?
「一番スケートやっていてよかったのは、スケートが強くなれたから言うわけじゃないけど、やっぱり有名になれたこと。人を介して有名になったんじゃなくて、自分で有名になったというのはありますよね。だから、引退後もいま人のために一生懸命やることができるんだなとはいつも思う。オリンピックには選手として3回行ったけど、スピード部門の監督として1回(2006年トリノ)、日本選手団総監督として2010年のバンクーバーにも行けた。ユニバーシアードにも団長として2回(2009、2011年)。僕が長年培ったものをスケート連盟に恩返しすることができた。とにかくトップにいかないと、こうはなれないわけだから、自分でもよくやったなという感じ。僕が死んだとき、みなさん方がこうやって取り上げてくれるのかどうか知らないけど、やっぱり人生のご褒美ですよ。僕はいま喜寿(77歳)だけど、「スケートやっていて、よかったな!」っていうのは、人生最後に言えるかもしれない。でも、いまは言わないよ。(笑)」
率直で飾らない語り口から、自分の信念を曲げず、スケートの道に邁進してきた一徹さが伝わってきた。いっぽう、現役時代からリンクでサングラスをした姿が話題を呼ぶなど、おしゃれでスマートな一面も。規格外のアスリートは、とかく人を惹きつける魅力にあふれた紳士だった。

日本スケート連盟特任相談役
鈴木 惠一
1942年生まれ
北海道苫小牧市出身
1964 インスブルックオリンピック 500m 5位
1968 グルノーブルオリンピック 500m 8位
1970 世界スプリント選手権 総合2位
1972 札幌オリンピック 500m 18位 日本選手団の主将、選手宣誓の大役を果たす
1963~1971年まで国内での500m競技では1度しか負けなし
1964~1970年まで世界選手権に7回出場し、3連勝含め5回優勝
500m世界記録更新は、世界タイ記録を含めて6回
2004~2010 日本スケート連盟理事・スピード強化部長
2010~2013 日本スケート連盟副会長
2006 トリノオリンピック スピード競技監督
2010 バンクーバーオリンピック 日本選手団総監督
著書 「スピードスケート」(1974年)